ドップラー効果とは:定義・原理・相対速度で変わる音波・光波の例
ドップラー効果の定義・原理を図解で簡潔解説。相対速度による音波・光波の変化の具体例と日常・天文での応用をわかりやすく紹介。
ドップラー効果とは、波の観測者が受け取る周波数(および波長)が、波を発するもの(発信源)と観測者との相対的な運動によって変化する現象です。波を作るもの(原因者)と、その波を見たり聞いたりしているもの(観測者)との間の距離が変化すると、観測される波の周期が短くなったり長くなったりします。一般的には、発信源と観測者が近づくと周波数は高く(波長は短く)、遠ざかると周波数は低く(波長は長く)なります。
基本的な原理
ドップラー効果は波そのものの性質(音波、光波、水面波など)に依存しますが、考え方は共通です。重要な点は「相対速度」です。発信源と観測者のどちらが動いているか、また媒質(音なら空気)の有無によって式が変わります。
- 音波(媒質あり)の古典的式:音速を v、発信源の周波数を f、発信源の速度を vs(観測者に向かってくる向きを正)、観測者の速度を vo(発信源に向かって動く向きを正)とすると、観測される周波数 f' は概ね次のように表されます。 f' = f × (v + vo) / (v − vs) (符号の取り方は慣習により異なるため、近づく向きは分子を増やす/分母を減らす方向に扱います。)
- 光波(媒質不要、相対論的効果):光のドップラー効果では特殊相対性理論が必要です。発信源と観測者の相対速度が大きいと、ローレンツ変換により周波数の変化は次のようになります(正面衝突・正対の場合)。 f' = f × sqrt((1 + β) / (1 − β)) ただし β = v/c(相対速度を光速 c で割った値)です。これにより接近時は青方偏移(周波数増大)、遠ざかると赤方偏移(周波数減少)になります。
- 横方向ドップラー効果(相対論的):観測者と発信源が直角方向に運動する場合でも相対論的には時間の遅れ(時間膨張)により周波数変化が生じます(これを横ドップラー効果と言います)。
身近な音の例
よく知られた例は走行中の車や救急車のサイレンです。救急車が近づいてくると聞こえる音の高さ(ピッチ)が高く、通り過ぎたあとは低くなります。これは発信源(サイレン)と観測者の相対速度が変化するためです。
簡単な数値例:サイレンの周波数 f = 1000 Hz、音速 v = 343 m/s、救急車の速度 vs = 30 m/s として、観測者が静止(vo = 0)の場合、近づくときの観測周波数は
f' ≈ 1000 × 343 / (343 − 30) ≈ 1095 Hz
通り過ぎた後(遠ざかる)では
f' ≈ 1000 × 343 / (343 + 30) ≈ 918 Hz
このように明確なピッチの変化が生じます。
光波の例と天文学での応用
光に対するドップラー効果は天文学で非常に重要です。恒星や銀河が地球から遠ざかっていると観測される光が赤方偏移し、近づいていると青方偏移します。これを使って銀河の後退速度を測り、宇宙の膨張や天体の運動を調べます。
反射とレーダーの利用
波が物体に反射して戻る場合もドップラー効果が利用されます。レーダーやソナーでは、送信した波が移動する目標で反射されると、戻ってくる波の周波数にずれが生じます。この周波数ずれから目標の速度を測定できます(例:交通取り締まり用レーダーや気象レーダー)。ここでの「反射」は波の方向が変わることを意味し、その際の周波数変化は発信源(観測装置)と移動体との相対速度に依存します。
まとめと注意点
- ドップラー効果はすべての種類の波で起こるが、媒質の有無や速度の大きさによって扱い方が異なる。
- 音波では媒質(空気等)が重要で、古典力学的な式が使える場合が多い。
- 光や高速で運動する粒子の場合は相対論的効果を考慮する必要がある。
- 符号の取り方(どちらを正とするか)に注意すると、式の適用ミスを避けられる。
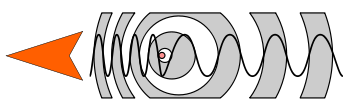
移動する物体によって引き起こされる波は、ドップラー効果を引き起こす
距離の変化による影響

波の観測者と作成者の距離が近くなれば、周波数は高くなり、波長は短くなります。
- 光の場合、これはブルーシフトと呼ばれるスペクトルの青い方の色へのシフトを引き起こします。私たちに向かってくるものが速ければ速いほど、ブルーシフトは大きくなります。
- 音の場合は、音が高くなるようになります
観測者と制作者の距離が長くなれば、周波数は低くなり、波長も長くなります。
- 光の場合、これは赤方偏移と呼ばれるスペクトルの赤い端へのシフトを引き起こし、何かが速く遠ざかるほど、赤方偏移は大きくなります。
- 音の場合は、音の高さが低くなる。
光波も読み取ることができる、例として
- 電子レンジ
- ラジオ波
ドップラー効果の極端な例として、音速よりも速いスピードで飛ぶ飛行機があり、その音の壁が地上にどう聞こえてくるかがあります。
関連ページ
質問と回答
Q: ドップラー効果とは何ですか。A: ドップラー効果とは、波を発生させるものと、その波を測定したり見たり聞いたりするものとの間の距離の変化によって引き起こされる、波の周波数と波長の変化のことです。
Q: 何がドップラー効果を引き起こすのですか?
A: 波を作り出すものと、その波を測定したり見たり聞いたりするものとの間の距離の変化がドップラー効果を引き起こします。
Q: ドップラー効果の "原因 "は何ですか?
A: ドップラー効果における「原因」の別の言葉は「送り手」または「源」です。
Q: ドップラー効果における「距離の変化」の別の言葉は何ですか?
A: ドップラー効果における「距離の変化」の別の言葉は「速度」または「相対速度」です。
Q: あらゆる種類の波がドップラー効果の影響を受けるのですか?
A: はい、物体から発せられる波、物体によって反射される波はすべてドップラー効果の影響を受けます。
Q: ドップラー効果における反射とは何ですか?
A: ドップラー効果における反射とは、波の方向が変わることを指します。
Q: 波の送り手はドップラー効果を体験できますか?
A: いいえ、波の送り手はドップラー効果を体験しません。
百科事典を検索する