百年戦争とは:フランスとイングランドの1337–1453年戦争ガイド
百年戦争の背景・経過・主要戦役をわかりやすく解説。エドワード3世からジャンヌ・ダルク、アギンクールやカスティヨンまで1337–1453年の完全ガイド。
百年戦争は、中世末期にフランスとイングランドの間で起きた、一連の軍事・政治紛争の総称です。通説では1337年から1453年までの約116年間を指しますが、実際には断続的な戦闘と長期の休戦(停戦)が繰り返された「連続する戦役群」でした。戦争の背景には王位継承をめぐる法的・封建的な争い、領土問題、経済的対立、同盟関係の対立などが重なっています。
発端と王位継承問題
争いの発端は、1328年にフランスのシャルル4世が、直系の男性の相続人(息子や弟)がいないまま死亡したことにあります。これに対し、イングランドのエドワード3世は、自分が母親を介してフランス王位を継承する権利があると主張しました。しかしフランス側は外国王を望まず、フランスのフィリップ6世は、サリク法(サリカ法)に基づき女性経由の継承を否定して自ら王位を主張しました。こうして王位継承問題が国際紛争へと発展し、両国は戦争状態に入ります。
序盤の戦況と戦術的変化
戦争開始時点では人口・資源の面でフランスが有利でした。イングランドの人口は約400万人だったのに対し、フランスは約1700万人を抱えていました。しかし海上戦力や弓兵を中心とした戦術的優位、同盟関係の巧妙な運用でイングランドは対抗しました。イングランドはフランスに対しスコットランドと敵対関係にある点を利用され、フランスはイングランド側が低地の一部と同盟関係を築こうとしたことが相互不信を深めました。
1340年のスルイスの海戦ではイングランドが海上で勝利し、対仏上陸作戦や補給線の維持がしやすくなりました。1346年のクレシーの戦いでは、イングランドの長弓兵(ロングボウ)と歩兵中心の戦術が重騎兵中心のフランス軍に対して大きな成果を上げ、戦争の様相を変える契機となりました。
黒死病とポワチエ、ブレティニー(ブレティニー条約)まで
1348年から1351年にかけてヨーロッパを襲った黒死病(ペスト)は両国に甚大な人口減少と社会・経済の打撃を与え、戦闘は一時的に落ち着きました。しかし復活した戦闘の中で、黒太子エドワードが率いるイングランド軍は1356年のポワチエの戦いでフランス王ジョン2世はこの戦いで捕虜となるなど大きな勝利を収めました。
その後の停戦や交渉により、1360年のブレティニー(Bretigny)条約などを経て一時的にイングランド側有利の条約が結ばれ、イングランドはフランス領土の広い地域を獲得しました(当時の領有は一時的にフランス領の約4分の1に相当するとされます)。しかしこの条約は恒久解決にはならず、その後も領土の奪還・争奪が続きます。
フランスの反撃と王権の回復
フランスの新王シャルル5世は、治世において軍事・財政を立て直し、ベルトラン・デュ・ゲスクランを有能な軍指揮官として起用することで戦況を好転させました。フランスは海上や内陸の補給・防衛を強化し、イングランド支配下の町を徐々に奪還しました。フランスはまたカスティーリャと同盟を結び、イングランド側が有利だった情勢に対抗する外交的戦略を採りました。
1389年から1415年の間には比較的長い和平が続きますが、王位継承問題や貴族間の対立、王権の弱体化などにより緊張は解消されませんでした。
再燃とヘンリー5世の侵攻
戦争のもっとも知られる再燃は1415年に起き、イングランドのヘンリー5世が大規模にフランスへ侵攻しました。ヘンリー5世は多くの弓兵を用いてアギンクールの戦いで決定的な勝利を収め、フランスの貴族層に大きな打撃を与えました。当時のフランス王であるシャルル6世は正気を失って支配が安定せず、王室内の派閥争い(ブルゴーニュ派とオルレアン派など)が事態をさらに混乱させました。
その後、フランス王妃バイエルンのイザボーは、娘の一人をヘンリー5世と結婚させる政治的決定を採り、両国はトロワ条約で妥協しました。条約によりヘンリー5世はフランス王位継承権を認められましたが、両国の関係は複雑なままでした。ヘンリー5世とシャルル6世はほぼ同時期に亡くなり、イングランド王位を継いだ若いヘンリー6世がフランス王を自称する状況が続きました。一方、シャルル6世の息子であるシャルル7世は、自らの正統性を主張して王位を巡る内戦的状況に直面しました。
ジャンヌ・ダルクの登場と戦争終結への転機
1429年、ジョーン・オブ・アークが現れて軍を鼓舞し、オルレアン包囲戦の解放やパタイの戦いでの成功によりフランスの士気を回復させました。彼女の軍事的・象徴的役割により多くの都市が奪還され、シャルル7世は正式に王として即位しました(即位させたが、)。ただし彼女は最終的に捕らえられ異端・魔術の罪で有罪とされ火刑に処されます。
ジャンヌの死後もフランスは徐々に勢力を回復しました。1435年のアラス条約で外交的勝利を収めたことは転換点の一つで、ブルゴーニュ公国の和解などで国際的な環境がフランス側へ傾きました。最終的に1453年のカスティヨンの戦いでフランス側が勝利し、これをもって中世的な百年戦争は事実上終結しました(同年、英仏の戦闘はほぼ終息し、英領残存地はカレーなど限られた拠点のみとなりました)。
戦争の特徴と影響
- 断続性:百年戦争は連続した「長期紛争」であり、和平・停戦と戦闘の波が繰り返されました。
- 軍事技術と戦術の変化:長弓兵や歩兵の活躍、火薬を用いた砲兵(後期の大砲)の導入などにより、重装騎兵中心の古い戦術が変容しました。
- 国家形成への影響:戦争とその負担は王権強化や中央集権化を促し、近代的な国王国家へと向かう過程を早めました。税制や常備軍の基盤が整っていきます。
- 社会・経済的影響:戦争と黒死病の複合的影響で人口が減少し、農業・都市経済・労働市場が大きく変動しました。傭兵や盗賊(ルーティエ)問題も深刻化しました。
- 領土の帰趨:最終的にフランスは大半の領土を回復し、イングランドは本国に専念する形へ移行しました。英仏間の領土関係は以後変化していきます。
- 文化的記憶:ジャンヌ・ダルクなどの人物は国民的英雄として後世に強い影響を残し、百年戦争は両国の歴史認識に深く刻まれました。
主な年表(要点)
- 1328年:シャルル4世死去(王位継承問題の発端)
- 1337年:戦争の開始年とされる
- 1340年:スルイスの海戦(英海軍の勝利)
- 1346年:クレシーの戦い(長弓の活躍)
- 1348–1351年:黒死病の流行
- 1356年:ポワチエの戦い(フランス王捕虜)
- 1360年:ブレティニー条約(停戦と領土の移転)
- 1415年:アギンクールの戦い(ヘンリー5世の勝利)
- 1429年:ジョーン・オブ・アークの登場、オルレアン包囲戦解放
- 1435年:アラス条約(外交的転換)
- 1453年:カスティヨンの戦いで決定的敗北、戦争終結(百年戦争の事実上の終わり)
百年戦争は単なる二国間の闘争を越え、軍事技術、国家体制、社会構造に深い影響を与えた歴史的出来事です。断続的な戦闘と停戦、地方領主と王権の対立、疫病や経済的圧力が絡み合い、近代への移行を促す重要な契機となりました。
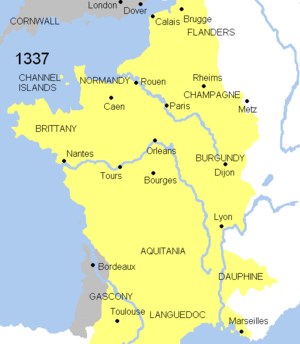
戦時中の時間スケールの地図。
質問と回答
Q:百年戦争とは何ですか?
A:百年戦争は、中世後期の1337年から1453年にかけて、フランスとイギリスの間で戦われた紛争です。
Q:戦争はどのくらい続きましたか?
A: 戦争は116年続きました。
Q: 何が百年戦争を引き起こしたか?
A: 百年戦争は、1328年にフランスのシャルル4世が男子の後継者を残さずに亡くなったことから、イングランドのエドワード3世が、自分の母親を通してフランスの王になる権利があると考えたことから始まりました。フランスの法律では、女性が統治したり、息子に権利を譲ったりすることは禁じられていたため、この意見の相違をめぐって両国は戦争に突入したのです。
Q: フランスのシャルル4世とは誰ですか?
A: フランスのシャルル4世は、1328年に直系男子の相続人を持たずに亡くなった王で、これが百年戦争の始まりとなりました。
Q: シャルル4世の死後、自分にはフランス王になる権利があると信じていたのは誰でしょう?
A: イギリスのエドワード3世は、シャルル4世の死後、自分の母親を通してフランス王になる権利があると信じていました。
Q: フランスの法律では、なぜ女性が統治したり、息子に権利を伝えたりすることを認めなかったのですか?
A:フランスの法律は、土地や爵位を相続できるのは男性だけであるとするサリック法に従っていたため、女性の統治や権利の継承を禁止していたのです。
Q: このイギリスとフランスの不一致の結果、何が起こったのでしょうか?
A: このイングランドとフランスの不和の結果、両国は戦争に突入し、いわゆる百年戦争が始まりました。
百科事典を検索する