アザミとは:キク科のトゲを持つ植物 — 定義・種類・特徴・象徴
キク科アザミの特徴・種類・象徴を解説。鋭いトゲの生態的意義から分類とスコットランドの花章まで、写真付きでわかりやすく紹介。
アザミは、キク科の植物で、花の周りに鋭いトゲを持つ植物である。茎や葉の平らな部分など、植物全体にトゲがあることが多い。これは、草食動物が植物を食べるのを阻止するために、植物を保護するものである。
アザミという言葉は、Cynareae(シノニム:Cardueae)グループに属する植物、特にCarduus属、Cirsium属、Onopordum属を正確に意味するとされることがある。しかし、このグループ以外の植物をアザミと呼ぶこともあり、そうするとアザミは多系統のグループを形成することになる。
アザミはスコットランドの花の紋章です。
定義と分類のポイント
一般に「アザミ」と呼ばれる植物は、キク科で頭状花序(複数の小さな花が集まって一つの花のように見える構造)をつくり、総苞(花の基部を取り巻く苞葉)や葉縁に刺があることが多い種類を指します。分類学的には先述のように主にCarduus、Cirsium、Onopordumなどが含まれますが、地域や文献によって呼び方が異なり得ます。
主な種類(例)
- Cirsium vulgare(バラアザミ、英名:bull thistle)— 広く分布し、茎や葉に強い刺がある。
- Carduus nutans(ムスクアザミ、英名:musk thistle)— 高さが出やすく、侵入生物として問題になる地域がある。
- Silybum marianum(マリアアザミ、ミルクシスル)— 種子が薬用・民間療法で利用されることがある。
- 日本本土には在来のCirsium属種が多数あり、地域名で呼ばれる山菜的利用のあるものもある。
外見と識別の特徴
- 花色:紫や紅色が多いが、白や黄色の種もある。
- 葉:羽状に裂けることが多く、葉縁に刺がある。葉面は被毛がある種もある。
- 花の構造:頭状花序を形成し、個々の小花(筒状花)が密に集まる。総苞の鱗片に刺があることが多い。
- 果実と種子:痩果(そうか)に冠毛(冠状の毛)がつき、風で散布されやすい。
生態・分布・繁殖
アザミは草地、荒地、道端、耕作地の縁など、日当たりが良くやや乾燥した場所を好みます。多年生、二年生、または一年生の種があり、種子散布で容易に拡散します。多くは花に多量の花蜜を出し、ハチやチョウ、その他の花粉媒介者を引き寄せるため、野外での生態系にとって重要な蜜源になります。果実の種子は風に乗って遠くまで飛ぶため、外来種として問題になることがあります。
人間との関わり:利用と管理
- 利用:若芽や茎は刺を取り除けば食用になるものがあり、一部の種(例:Silybum marianum)は伝統的に薬用に使われてきました。ただし、個々の種の扱い方や安全性は異なるため、採取や摂取の際は地域の知識に従うことが重要です。
- 園芸:観賞用に栽培される派手な品種もあり、庭にアクセントを加えることがありますが刺に注意が必要です。
- 管理:侵入性の高い種は農地や在来生態系に悪影響を与えるため、地域のガイドラインに従った防除や早期駆除が推奨されます。物理的除去、適切なタイミングでの刈取り、種子の散布を防ぐ対策などが用いられます。
象徴性・文化
アザミは防御や不屈の象徴とされることが多く、特にアザミはスコットランドの紋章(国章)として知られています。伝説では、ノルマンの侵入者が裸足でアザミを踏んで悲鳴を上げたためスコットランド軍が有利になった、という説話が語られます(史実かは諸説あります)。
取り扱い上の注意
アザミの刺は鋭く皮膚を傷つけることがあるため、採取や剪定を行う際は厚手の手袋や長袖を着用してください。また、一部の種はアレルギー反応を引き起こす場合があるので、触れた後に発疹やかゆみが出たら医師に相談してください。
以上がアザミの定義・種類・特徴・象徴に関する概要です。地域によって見られる種や呼称、利用法が異なるため、より詳しく知りたい場合は地域の植物図鑑や専門書、地方自治体の外来種情報などを参照してください。

ミルクシスル フラワーヘッド
分類
キク科で一般名にアザミという言葉がよく使われる属には、以下のようなものがあります。
- アークティウム - ゴボウ
- Carduus - Musk Thistle 他
- カーリーナ - カーラインアザミ
- ケンタウレア - スターアザミ
- Cicerbita - ソウハクアザミ
- Cirsium - コモンアザミ、フィールドアザミ、その他
- Cnicus - ブレスド・アザミ
- Cynara - アーティチョーク、カルドゥーン
- Echinops - Globethistle
- ノトバシス - シリアアザミ
- Onopordum - コットンアザミ(別名:スコッチアザミ
- Scolymus - ゴールデンアザミまたはオイスターアザミ
- シリクム - ミルクシスル
- ソンクス - ソウハクアザミ
キク科以外の植物でアザミと呼ばれることがあるものには、以下のようなものがあります。
- サルオガセ - 塩生植物、タンブルウィード、ロシアンアザミ(アカザ科)
紋章
アザミはアレクサンダー3世(1249-1286)の時代からスコットランドの国章とされ、1470年にジェームズ3世が発行した銀貨にも使われている。また、スコットランドの高等騎士団であるアザミ騎士団のシンボルでもある。スコットランドのシンボルとして、またスコットランドのサッカークラブの名称として多く使われている。スコットランドの王冠を冠したアザミは、スコットランドの8つの警察組織のうち7つの組織のシンボルである(例外は北部警察)。また、アザミはスコットランドのエディンバラで生まれたブリタニカ百科事典のエンブレムにもなっている。カーネギーメロン大学の紋章はアザミである。
スコットランドのシンボルとしての由来
伝説によると、北欧軍がスコットランドの野営地に夜忍び込もうとしていた。その際、裸足の北欧人が不運にもアザミを踏んでしまい、痛みで叫び、北欧人の侵入をスコットランド人に知らせたという。北方諸島とヘブリディーズ諸島を支配し、何年にもわたってスコットランド王国の沿岸を苦しめてきたノルウェー王ハーコン4世(Haakon the Elder)の旅立ちを告げるラルグの戦いがその具体例だとする資料もある。この伝説では、どの種のアザミを指しているかは議論の分かれるところである。現代では、中世のスコットランドに生息していたとは考えにくいが、その堂々とした姿からコットンアザミ(Onopordum acanthium)がよく知られている。その他、Dwarf Thistle Cirsium acaule、Musk Thistle Carduus nutans、Melancholy Thistle Cirsium heterophyllumなどの種が候補として挙げられている。
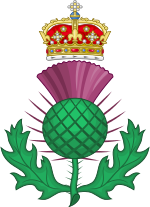
スコットランドのアザミをヘラルディックバッジとして使用。
医療用
プリニウスや中世の作家たちは、禿げた頭に髪を戻せると考えていたこと、近世には頭痛、ペスト、カンジダ、ただれ、めまい、黄疸の治療薬として信じられていたことをモード・グリーヴは記録している。
百科事典を検索する