古代インドとは:インダス文明からアショーカ・グプタ朝までの歴史概要
古代インドの始まりからアショーカ・グプタ朝まで、インダス文明・マウリヤ帝国・仏教拡散を分かりやすく解説。文化と政治の変遷を一挙に学ぶ歴史入門。
古代インドには、長きにわたる文明と文化がありました。現在のインド、パキスタン、バングラデシュを含む複数の国に及んでいます。地理的には、ヒマラヤ山脈から南のデカン高原、インダス川やガンジス川の流域まで多様な自然環境があり、それが地域ごとの生活様式や政治構造の差を生みました。
インダス文明(紀元前2600年頃〜紀元前1900年頃)
紀元前2600年頃から紀元前1900年頃まで栄えたインダス川流域文明は、亜大陸における都市文明の始まりです。主要都市としてはハラッパー(Harappa)やモヘンジョダロ(Mohenjo-daro)、ロータル(Lothal)、ドホラヴィーラ(Dholavira)などが知られています。これらはインダス川とその支流を中心に発展しました。
特徴としては、焼きレンガで構築された計画都市、整備された排水・下水システム、区画化された住居や倉庫、標準化された計量器具・印章などが挙げられます。農耕や家畜の飼育に加え、交易も活発で、メソポタミア(古代都市国家)との交易が考古学的に示されています。文字(インダス文字)は多数刻まれた印章に残されていますが、未解読のため内部の政治・宗教構造は完全には明らかになっていません。
衰退の原因としては、気候変動や河川の流路変化、土地の塩害、外来の移動・侵入など複合的な要因が想定されています。インダス文明の崩壊後、地域社会は再編され、後のヴェーダ時代へとつながります。
ヴェーダ時代と宗教・社会の変化(紀元前1500年頃〜紀元前500年頃)
インダス文明の後、北西からのインド=アーリア系の移動とされる流入によって、サンスクリット語の祖型となる言語や宗教的伝承が持ち込まれ、リグ・ヴェーダなどのヴェーダ文献が成立していきます。これに伴い、部族社会からより階層化された社会構造へ変化し、やがてヴァルナ(四つの身分)や多数の職業集団(ジャーティ)を特徴とする社会秩序が確立しました。
この時期には農業の発展とともに都市化が再び進み、複数の小王国(ジャナパダ)が形成されました。また、宗教的にはヴェーダの儀礼を中心とするブラフミン教的な要素のほか、既存の社会秩序に対する反省から生まれた仏教やジャイナ教といった導入宗教的な運動(いわゆる「異端」的思想)が台頭しました。これらは後の社会・政治に大きな影響を与えます。
マウリヤ帝国(紀元前321年〜紀元前185年)とアショーカ
紀元前321年に建国されたマウリヤ帝国は、チャンドラグプタ(チャンドラグプタ・マウリヤ)によって創始され、行政・軍事の整備を通じてインド亜大陸の大半を初めて統一しました。政治思想や統治技術においては、『アルタシャーストラ(政治経済学)』を伝えるカウティリヤ(チャーナキヤ)の影響が指摘されます。
アショーカ大王(在位およそ紀元前268年〜紀元前232年)は、特に有名な在位者で、当初は領土拡大を図ったものの、カリンガ戦争での多大な犠牲を見て仏教に帰依し、アヒムサ(非暴力)や善政を掲げました。アショーカは各地に石碑や柱を建て、政策や倫理的教えを刻ませました。これらはアショーカの勅令として現存し、インド最古級の史料群を提供しています。勅令はプラクリット語や古代ギリシア語・アラム語などでも刻まれ、国内外に向けたメッセージであったことがうかがえます。
マウリヤ期には中央集権的な行政、徴税・測量の整備、交易と手工業の促進が行われ、国際的にもヘレニズム世界や中央アジアと接触がありました。アショーカ期の保護のもと、仏教は南アジア内外に広がり、僧伽(サンガ)の組織化が進みました。
マウリヤ後の変遷とグプタ朝(約320年〜550年)
マウリヤ帝国の滅亡後は、諸王朝が興亡を繰り返し、ガンダーラやクシャーナ朝などの地域政権が北西インドを中心に力を持ちました。クシャーナ朝は中央アジアやシルクロードを通じて仏教芸術(ガンダーラ美術)を発展させ、仏教像の表現にヘレニズム的影響をもたらしました。
グプタ王朝(一般に「グプタ朝」と呼ばれる)は、4世紀頃から北インドを中心に勢力を拡大し、約5世紀にかけていわゆるインド古典期(古典文化の黄金時代)を形成しました。代表的な王にはチャンドラグプタ1世、スマトラグプタ(サムドラグプタ)、チャンドラグプタ2世(ヴィクラマディティヤ)などがいます。グプタ期は政治的安定の下でサンスクリット文学や学問、芸術、数学・天文学が飛躍的に発展し、詩人カリダーサの作品、学者アーリヤバータの天文学、ヒンドゥー教・仏教・ジャイナ教の学術的議論が盛んになりました。
この時期に十進法やゼロの概念が発展したほか、医学(スシュルタやチャーラカの伝統)、彫刻・寺院建築の基礎が築かれます。グプタ朝の衰退は5〜6世紀のフン(フン族、いわゆるフナ族)侵入や地方分権化によるもので、以後地域王朝が再び分立化していきます。
社会・経済・文化的成果
- 宗教と哲学:ヴェーダ宗教を基盤に、ヒンドゥー教の基礎、仏教・ジャイナ教の誕生と拡散が見られ、思索と実践の多様性が発展しました。
- 言語と文学:サンスクリット文学の成立、マハーバーラタやラーマーヤナなどの大叙事詩の成立(口承を含む)、プラクリットやパーリ語の文献も重要です。
- 科学技術・数学:天文学・数学(ゼロの概念、十進法、代数的知見)、医学(外科・内科の知識)などで著しい進展がありました。
- 芸術・建築:印章彫刻や陶器、ストゥーパ(仏塔)・石窟寺院・彫刻などの発展。後期には寺院建築の様式が確立されます。
- 交易・経済:内陸・海上交易、インド洋・アラビア海を介した国際交易、手工業の発展、貨幣経済の普及が進みました。
主要な遺跡・史料
インダス文明の遺跡(Harappa、Mohenjo-daro、Lothal、Dholavira)やアショーカの石碑・柱文(アショーカの勅令)、グプタ期の文献・石彫などが重要な史料です。これらの考古学的・文献的資料を総合することで、古代インドの政治・宗教・経済の全体像が徐々に明らかになっています。
終わりに
古代インドの歴史は、都市文明としてのインダス文明から、ヴェーダ的社会の成立、マウリヤ帝国による大規模統一、そしてグプタ朝に代表される古典文化の成熟へと連続的に展開します。各時代ともに宗教・思想・技術・芸術において重要な遺産を残し、南アジアだけでなくアジア全域に大きな影響を与えました。これらの変遷を通じて形成された制度や文化は、現代のインド亜大陸の諸文化にも深く関係しています。

釈迦如来立像 パキスタン北部ガンダーラ地方 1世紀 ギメ美術館蔵
主なイベント
年表
- 紀元前1500年~紀元前600年:『ヴェーダ』『ブラーフマーナ』の構成
- 紀元前700年~紀元前300年:ウパニシャッドの構成
- 紀元前527年または526年。ジャイナ教の創始者であるマハーヴィーラの死
- 6世紀後半。ペルシャ王ダリウス(召喚者の裂け目の王)、古代パキスタンの一部を征服
- 紀元前486年釈迦の死。中国では紀元前483年とされる。
- 紀元前400年:パニニーニが最初のサンスクリット語の文法を作る
- 紀元前4世紀~紀元前4世紀。ラーマーヤナ」と「マハーバーラタ」の作曲
- 紀元前327年~紀元前25年アレクサンダー大王がインダス川流域(現在のパキスタン)に侵入。
- 紀元前321年~紀元前181年チャンドラグプタ・マウリヤがマウリヤ帝国を建国
- 紀元前300年:メガステネス(ギリシャ人)がマウリヤ王を訪問
- 紀元前300年:「アルタシャストラ」の作曲(学者によっては紀元100年とする人もいる
- 紀元前268年~紀元前233年 アショカ大王の治世
- 紀元前185年~紀元前75年:スンガ朝がインド中央共和国を支配
- 紀元前2世紀~紀元前3世紀:インドにおける仏教・ジャイナ教の影響がピークに達する
- 紀元前1世紀~紀元後1世紀:シャカ、パルティア、クシャナがインダス川流域に侵入
- 紀元前1世紀~紀元後2世紀:サタバハナの支配
- 紀元前58年~紀元前57年ヴィクラマ・サムヴァートの時代が始まる
- 南部のチェラ、チョーラ、パンディヤの各王国
- 西暦78年:シャカの時代の始まり
- 1〜3世紀。クシャン朝の治世。ジャイナ教のティルタンカラやヒンドゥー教の双腕の神々が初めて描かれた。
- 4世紀から5世紀にかけてヴァクタカによる中央インドとデカン地方の支配
- 4〜6世紀。現在のインド共和国の大部分と中央部におけるグプタ時代(パキスタン地域は含まれていない)、ただしこの時期はガンジス川流域のインド黄金時代である。
- 西暦500年。アジャンタ完成
- 5~7世紀クリシャン教を中心としたヴァイシュナヴィズムの普及、地方の神々への崇拝の出現、タントラ教の台頭
- 5~6世紀古代パキスタンにおけるフン族の侵入
- 6~17世紀。西インドの各地域におけるラージプート族の支配。
- 6世紀カラチュリー王朝が現代インドの西海岸を支配
- 6〜8世紀南インドのパラヴァ王朝、南部で岩窟建築が始まり、ママッラプラマやカンチプラムで寺院建築が盛んになる。
- 6世紀から10世紀にかけてタミル語で書かれた献身的な詩
- 7~8世紀古代パキスタン、インド北部共和国における仏教の衰退、ヒンドゥー教の復興
- 7〜10世紀。ラシュトラクタ王朝がデカン北部を支配
- 8世紀初頭。アラブ商人がシンド(現在のパキスタンの一部)とインドのグジャラート州の海岸に移住
- 8〜12世紀。パラ王朝がビハール、ベンガル、およびインド東部の大部分を支配
- 10世紀~17世紀。西インドの各地域におけるラージプート族の支配。
- 西暦788年~820年アディ・シャンカラチャリヤの生涯
- 西暦1018年。最初のイスラム教徒の支配者、マフムード・ガズニがインドを襲撃。
- 1947年 インドが独立
- 1950年 インド共和国が成立
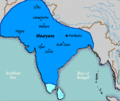
マウリャン帝国の最大範囲を紺色で示した地図。
質問と回答
Q:インダスバレー文明はどこで栄えたのですか?
A:インダス川とその支流を中心に、現在のインド、パキスタン、バングラデシュを含む数カ国で栄えた文明です。
Q:インダスバレー文明はいつごろ存在したのですか?
A:インダスバレー文明は、紀元前2600年頃から紀元前1900年頃まで存在したと言われています。
Q: インダスバレー文明の意義は何ですか?
A:インダスバレー文明は、亜大陸における都市文明の始まりを示すものです。
Q: マウリヤ帝国はいつ、誰が建国したのですか?
A:マウリヤ帝国は紀元前321年に建国され、地味な出自の無名の戦士によって設立されました。
Q: アショーカ大王は何で知られていますか?
A: アショーカは、仏教に改宗した後、アヒムサ(非暴力)の政策をとり、アショーカの勅令を使って東アジアと東南アジアに仏教の思想を広めたことで知られています。
Q: アショーカが仏教に改宗したのはいつですか?
A:アショーカは、古代インドのマウリヤ帝の時代に、当初は王国を拡大するために仏教に帰依しました。
Q: グプタは誰で、どんなことで知られているのですか?
A:グプタはグプタ時代の重要な支配者であり、賢く高貴な人物として知られています。
百科事典を検索する