鉄道砲とは?大戦を彩った列車砲の歴史・構造・衰退理由
大戦を彩った鉄道砲の歴史・構造・衰退理由を図解で解説。列車砲の実戦例や技術的特徴、消えた理由をわかりやすく紹介。
鉄道砲は、列車砲とも呼ばれ、特別に設計された鉄道貨車の上に据え付けられ、それによって運ばれ、発射される大型の砲兵器である。多くの国が鉄道砲を開発・配備したが、最もよく知られているのはクルップ社などが製造したもので、第一次世界大戦と第二次世界大戦でドイツが使用した事例が特に有名である。規模の小さい砲はしばしば装甲列車の一部として運用された。
歴史的背景
鉄道砲の起源は19世紀後半にさかのぼり、重い要塞砲や沿岸砲を陸上で移動・配備する手段として発展した。第一次世界大戦では、固定砲や牽引砲では運搬が困難な大口径の砲を戦線近くまで移動させるために鉄道砲が多用された。とくに長射程を誇るものや一撃の威力が大きいものは、敵陣地や都市を遠距離から砲撃するために使われた。
第二次世界大戦でも鉄道砲は一部で重要な役割を果たした。ドイツは極めて巨大な口径を持つ鉄道砲(例:シュヴェレル・グスタフ/ドーラのような80cm級の超大型砲)を製作し、要塞破壊や長距離砲撃に投入した。これらは製造・運用に莫大な費用と工数を要したが、当時の技術的限界のもとで得られる最大級の火力を提供した。
構造と主要な特徴
- 台車・砲架:砲は専用の台車(複数車軸がある重車台)や旋回台に据え付けられる。旋回性能は装置によっては限定的で、射角調整のために線路の曲線や転車台を使うことが多い。
- 反動吸収:大口径砲の反動は極大なので、油圧や空気ばね、滑走式の砲架などで反動を吸収し、車体や線路への負担を軽減する工夫が施される。
- 装填・弾薬処理:砲弾は非常に重く、専用の弾薬車や起重機(クレーン)で装填する。装填作業は時間がかかり、連射性は低い。
- 基礎設営:発射時は補助ジャッキやアウトリガーで車体を固定することが多い。超大型砲では専用の側線を敷設したり、軌道補強を行ったりする必要があった。
運用上の利点と用途
- 大口径で大重量の弾を運用でき、敵要塞・防御陣地・港湾施設へ強い破壊力を与えられる。
- 鉄道網を利用して比較的迅速に重火器を移動・集結できる点は、固定砲より機動性があった。
- 長射程砲は戦略的な都市や後方施設への遠距離砲撃に適していた。
欠点と脆弱性
- 軌道に依存するため行動範囲が限定され、線路を破壊されると運用不能になる。
- 巨大な車体や発射準備のために目立ちやすく、航空偵察や爆撃の格好の標的になる。
- 弾薬補給や整備に多大な人員・物資が必要で、柔軟な戦術運用に向かない。
- 発射頻度が低く、射撃後の移動にも時間がかかるため、即応性に乏しい。
衰退の理由
鉄道砲が広く使われなくなった理由は複合的である。まず航空機の発達により、移動中や発砲地点での航空攻撃・爆撃に対する脆弱性が増した。加えて、戦後は高性能の自走砲や牽引砲、さらには弾道弾・巡航ミサイル・精密誘導兵器の発達により、同等の破壊力をより柔軟かつ秘匿的に発揮できるようになった。特に航空攻撃やロケット・ミサイルの精度・射程の向上は、鉄道砲の戦術的優位性を消失させた。要約すると、巨体ゆえの目立ちやすさ、軌道依存性、運用コストの大きさが主な衰退要因である。最後に一言で言えば、航空機やロケット弾、ミサイルに取って代わられたためである。
現存例と遺産
実戦で使用された多くの鉄道砲は戦後に解体・廃棄されたが、一部は博物館や屋外展示として保存されている。保存品は戦争技術史や軍事工学の興味深い資料であり、当時の砲兵運用や兵站の規模を伝える貴重な証拠となっている。現在では、鉄道砲は大規模兵器の一例として歴史・軍事技術の研究対象になっている。
まとめ
鉄道砲は一時代を代表する「超重量砲兵」だったが、技術革新と戦術の変化によりその存在意義を失っていった。重火力という利点はあったものの、目立ちやすさ・柔軟性の欠如・高コストが運用上の大きな制約となり、現代の戦場ではほとんど姿を消している。

第一次世界大戦中のフランス製370mm鉄道榴弾砲
歴史
鉄道砲の構想は、1860年代にアンダーソン氏によって初めて提案された。彼はイギリスで「National Defence」という小冊子を出版し、その中で鉄道車両の鉄壁化計画を提案した。1860年にロシア人のレベデウが鉄道車両に迫撃砲を搭載したのが最初の発明とされている。[] 。
最初に戦場で使われた鉄道砲は、帯状の32ポンド砲ブルック海軍ライフルであった。南北戦争では、この銃は平らな鉄道車両に搭載され、鉄板で保護されていた。1862年6月29日、ロバート・E・リーはこの銃を機関車に押させてリッチモンドとヨーク川の線路(後に南部鉄道の一部になる)を越え、サベージズステーションの戦いで使用したのである。また、バージニア州ピーターズバーグの包囲戦で、鉄道車両に搭載された北軍の13インチ攻城迫撃砲の写真もある。ディクテーター(Dictator)またはピーターズバーグ・エクスプレス(Petersburg Express)というニックネームで呼ばれた。
鉄道砲は、1870年のパリ包囲戦ではフランスが、第2次ボーア戦争ではイギリスがレディスミス包囲戦で使用した。
第一次世界大戦
ドイツは第一次世界大戦開戦時にすでにビッグ・バーサ砲を数門持っていたが、フランスは重野砲が不足していた。大型の海岸防衛砲や海軍砲が前線に移された。これらは通常、野戦での使用には適さず、何らかの搭載方法が必要であった。鉄道砲はその解決策となった。1916年には、両陣営とも鉄道砲を使用するようになった。
ボールドウィン機関車製作所は、1918年4月から5月にかけて、アメリカ海軍の列車に14インチ/50口径の鉄道砲を5門製作しました。各列車にはMk 4 14"/50口径砲が搭載された。これらはニューメキシコ級とテネシー級戦艦に使用された14インチ(360mm)の海軍用ライフル銃で、4つの6輪台車を持つレールキャリッジに搭載された。この砲の1つがワシントン海軍工廠の博物館の外に展示されている。
第二次世界大戦
第二次世界大戦では、鉄道砲が最終的に使用された。ドイツ軍が使用したのは80cmの巨大なシュベラーグスタフ砲で、これは戦場で使用された最大の砲であった。航空機の台頭により、鉄道砲の使用は事実上終了した。戦艦と同様、大きく、高価で、空から簡単に破壊されるからである。

ペテルブルグ攻防戦に使用された鉄道砲
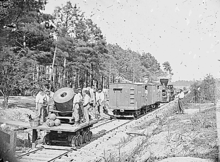
独裁者」ペテルブルグ(マチュー・ブラディ)

ボーン・パーク・トンネル内から見たボシュ・バスター(1941年3月21日、ケント州ビショップボーンにて
現存する鉄道砲
- バージニア州ダールグレンにある海軍水上戦闘センター・ダールグレン分室に12インチ鉄道砲があります(画像と簡単な説明はこちらのリンクをご覧ください)。
- 第一次世界大戦時の米海軍14インチ/50口径鉄道砲がワシントン海軍工廠にある。
- アメリカ陸軍兵器博物館には、ドイツのクルップ社製K5砲(「アンツィオ・アニー」)が展示されています。アンツィオ海岸を砲撃した2挺のドイツ軍砲の部品を使用して作られたものである。連合国軍に捕獲される前に、乗組員によって一部破壊された。また、フランス北部のオーディンゲン近郊にあるバッテリー・トッド博物館には、2基目のK5が展示されている。
- ソ連時代の305mm MK-3-12砲は、ロシアのロモノーソフ近郊のクラスナヤゴルカ要塞とサンクトペテルブルグの鉄道技術博物館で展示されている。ソ連のТМ-1-180 180mm砲はクラスナヤ・ゴルカ要塞、モスクワの大祖国戦争博物館、ウクライナのセヴァストポリ鉄道駅で見ることができる。
· 
クルップK5、アメリカ陸軍兵器博物館
· 
クルップK5、バッテリー・トッド博物館(フランス
·
ロシア、クラスナヤゴルカ要塞、MK-3-12
·
TM-1-180, クラスナヤゴルカ砦
· .jpg)
サンクトペテルブルグ鉄道技術博物館 MK-3-12
· 
TM-1-180、大祖国戦争博物館、モスクワ
· 
ウクライナ、セバスタポール市、TM-1-180
·
コンデ・デ・リンハレス軍事博物館(ブラジル
·
第一次世界大戦時のドイツ製28cmブルーノの砲身(キャンベラ、オーストラリア戦争記念館にて
百科事典を検索する



